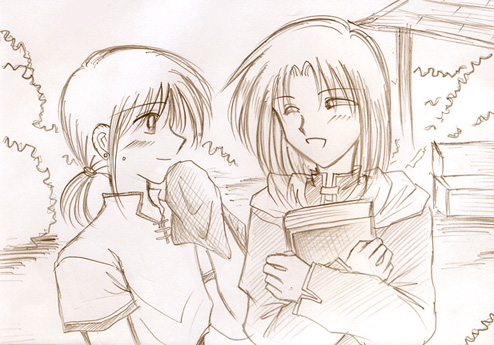
RASYARD Prologue
さらさらと頬を撫でる風は、どこまで優しい。
春の陽光は暖かく降り注ぎ、ここ――ソラテスの王宮にも、変わらぬ温かみをもたらしている。
白い大理石の柱は陽光を受けてキラキラと輝き、それを見上げるには、少々眩し過ぎるほどで。
今となってはキレイに修復されたその柱を見るにつけ、『時』の経過を自覚する。
あれから。
あの『事件』から、一体どれほどの時が経ったのだろうか。
10年。人の子が産まれて、自我を持つまで。
たったそれだけの時なのに、人々はみな、それらを無かった事の様にしている。
――忘れられるものか。
そうだ、忘れられない。忘れられるわけが無い。
10年前のあの日、この王宮で起こったあの事件を忘れる事などあり得ない。
時が経ったのは事実だけれど、あの時起こったことも、紛れも無い現実。
それを忘れてのうのうと平穏に過ごす事などできはしないのだ――少なくとも、一部の人間には特に。
眩しそうに柱を見上げて、その上に広がる蒼い空を見上げる。
その空に溶けてしまいそうな、見事な蒼みがかった銀髪の青年。
彼にとっては―――それは殊更強く思える事。
「こちらにおいでだったのですか」
ふいに声を掛けられて、それでも、空を見上げたまま。
声を掛けた人物は振りかえらない青年を見やって、ため息を一つ。
「王子――お気持ちは分かりますが」
「ヴェルヌ」
「はい」
「お前は、忘れたわけではないよな?」
10年前のあの日の事。
忘れられない、忘れてはいけない、あの『事件』。
声を掛けてきた人物に真っ直ぐな視線を向けながら、青年は静かに問う。
「…忘れる事など…あり得ませんよ、レオン様」
青年の真摯な瞳に観念した様に答えて、それでも、と言葉を続けた。
□■□■□■□■□■
ほんの10年前。
その絶大なる魔力を持った『大神官』アルファー=ルナの最高の庇護の元、最高の軍事力とを併せ持った
皇国マーヴェラスは平和だった。
その広大な領土の中でも首都・アデルのある中央大陸は温暖な気候で、豊潤な大地には草木も家畜もその
恩恵に預かり、人々もその日々の幸せな糧を大切に慈しみ、人も国も栄えに栄えていた。
時の皇帝は多少病弱であったものの名君の誉れも高く、その後継ぎである第一王子ラウルは、
その少女と見まがうほどの美少年ぶりは勿論のこと、魔法力に長け頭脳も明晰、父譲りの名君の才覚を覗かせるほどと、
周囲の期待にいつも見事に応えていた秀才だった。
その弟である第二王子レオン。彼は兄とは違った少年らしい風貌で、魔法の才覚すら見出されなかったものの、その剣術における才覚は目覚しく、
時の若き親衛隊長ウィルナードが自らその教育・指南係を買って出たほどだった。
第一王子は、天才の誉れも高い大神官アルファー=ルナの側近、セイドリックを教育係に。
第二王子は、剣術に掛けては右に出る者のない若き親衛隊長、ウィルナードを教育係に。
兄弟二人は仲良く互いの才覚を認め合い、国はその有能な世継ぎに次代の平和をも確信していた。
「よ、側近殿。今帰りかい?」
そんな有能な世継ぎと共に王宮の廊下を歩いていたセイドリックに掛けられた、軽口。
仮にも王子が共にいるというのにそんな言葉を投げかけられたセイドリックは、ため息混じりに振りかえった。
「ウィル…お願いですからもう少し気遣ってくださいませんか。ラウル様もご一緒なんですよ?」
「それは勿論。ラウル殿下、本日の訓練は如何でしたでしょうか」
「ウィル!!」
王子の前に膝をついて軽くウィンクをしながらそう言った相手に、セイドリックはその女性とも見まがうほどの美しさと
優しさを兼ね備えた風貌を、困った様に歪めて小さく叫んだ。
けれども当のラウル王子は、クスクスとおかしそうに笑った。
「うん、とっても楽しかったよ。ウィルナードはどうだった?レオンも一緒なんでしょ?」
「楽しい?そては頼もしい…レオン様も、じき戻られると思いますよ」
「じき?」
「ええ、じき、です。今王宮の廻りを走って頂いていますから」
「走りこみ?」
「ええ、体力勝負ですからね、我々は」
そう言って悪戯っぽく笑う男は、とても戦場で『黒衣の悪鬼』と怖れられているとは思えない。
親衛隊長、ウィルナード=ヴァン・ガーディス。
代々武官を勤め上げてきた名門ガーディス家の長男であり、マーヴェラスの若き親衛隊長。
その剣術は国で一番、100年に一度の天才とさえ言われている。
「まったく…ラウル様も少しはお咎めになっていただきませんと…」
「でも、この方がウィルらしくていいよ。僕もレオンもこうやって気さくに接してくれた方が嬉しいし」
「ほーら、王子のお許しだ。あまりやかましい事ばかり言ってるとヴェルヌみたいに剥げるぞ、お前」
「……ヴェルヌが可哀相なのはどなたのせいですか…」
セイドリックのため息混じりの言葉に、ラウルとウィルナ―ドが笑った。
つられて、セイドリックも苦笑する。
この場に居ない生真面目で苦労性の政務官ヴェルヌホーンと、ウィルナードとセイドリック。
三人は若いながらもこの国を支える重要な柱とされている。
互いの間柄も立場こそ多少の違いはあれど、幼馴染という気安い間柄で。
王子二人にとってもその三人はなんらかの教えを受けている『教師』であり、気の許せる存在だった。
「…あ、そろそろ弟君が戻られますよ、ラウル様」
「ほんと?」
笑みを顔に残したまま、ウィルナ―ドが立ち上がって右方向を指し示す。
た、た、た、と。
軽快な足音が響いてきて、やがて。
蒼空の色をそのまま写したような青味かかった銀色の髪が現れる。
そして――。
「―――げ」
懸命に走る弟王子の背後からゆっくりと歩んでくるのは。
なんとも言えぬ表情をした、生真面目で融通の利かないと噂されたヴェルヌホーン、その人だった。
「まったくお前の行動は全てが信じられん!!」
開口一番、叫ぶ。
「どこの世界に王子だけを走らせる指南役がいるんだ!」
怒り心頭に達しているらしいヴェルヌの剣幕にも、ウィルナードは軽い笑みを崩さない。
「よう、政務官殿。会議は終わったのかい?」
「私の問いに答える気はないのか!ウィルナード=ヴァン・ガーディス!」
「なくはないがね。その前に王子の介抱をしても構わないかな?」
「当然だろう!!」
怒鳴りながらも、理性を失わないヴェルヌに苦笑しながら、息せき切って走りこみを終えた王子に、ウィルナードは膝をついて頭をたれる。
「失礼を、レオン様。どうぞゆっくりと息を吸い込まれてください」
「だ…ぃ、じょうぶ、ありが…と」
そう言ってにっこり笑みを返すと、弟王子・レオンは兄のラウルを振り返った。
「兄上は…、もう、終わり?」
「うん。今日は、ルナの祝詞の日だからね」
「あぁ…そ、か。セイドリック、お手伝いに行くんだね」
週に一度の、最高神官の『祝詞』の日。
国を、王を、国民を称え、その全てに祝福を与える日。
最高神官であるアルファー=ルナの側近であるセイドリックは、そのルナの『祝詞』の力を国に行き渡らせる手助けをしているのだ。
そんな日だけは、必然的に兄王子への魔術指南が早めに終えられる。
「じゃ、我々もこれで終わりに致しましょうか、レオン様」
「え?でも…」
当初ウィルナードに言われていた修練プログラムは、まだ2つほど残っていたはずだったので、レオンは目を丸くしてその長身の青年を見上げた。
ウィルナードはそんなレオンの視線を真っ直ぐに受け止めて、にっこりと笑う。
「構いませんよ。せっかくお二人でお話できる時間が出来たのですから、今日はこれまで。あとは明日に致しましょう」
「あ…ありがと!」
レオンもまた満面の笑顔で、嬉しそうに笑った。
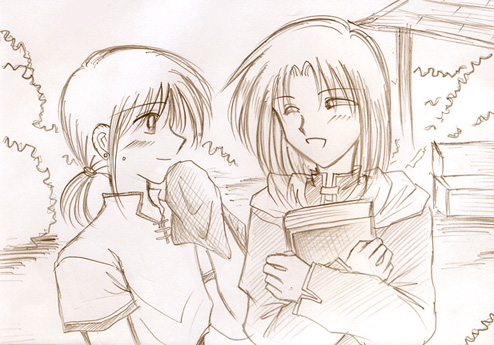
「じゃあレオン、またあの話をしようよ!」
「旅の?」
「そう、旅の!」
修練を終えたばかりの弟の手をとって、ラウルが人差し指を立てて片目を瞑った。
そう、こんな風に二人でゆっくり話す時間が取れたときには、必ずする『話』。
「いつか、僕ら二人と…セイ、ウィル、ヴェルヌの五人で、旅に出る話!」
そんな事が無理だという事はわかっていても、まだ幼い王子二人はその『夢』を諦めることはなかった。
そしてそんな彼らの『夢』を、ウィルナードは勿論、他の二人の忠臣もわざわざ否定することもなかった。
やがていつかは、そんな『夢』を見たことを懐かしむ時がやってくる。それでいいと思っていたから。
手を取り合って、楽しそうに笑いながら小走りに掛けていく王子二人。
その背中を見つめながら、忠臣であり、また若き重鎮でもある三人は、いつまでもあの二人が仲良くいられるよう、祈らずにはいられなかった。
「素直で良いお子ですね、お二人とも」
「ああ、まったく」
「教育係がお前で、正直私は懸念もしていたぞ。セイドリックはともかく」
「そりゃどういう意味だよ」
「あまりに庶民的過ぎても困る、という事だ。やはり『王太子』である以上は…」
そこまで言いかけたヴェルヌの口を閉じさせるように、ウィルナードがにっと快活に笑った。
「ま、心配ないさ。殿下はどちらもその辺はきちんと分かってらっしゃるよ」
「……相変わらず楽天的だな」
「悩んでも仕方のない事なら、楽天的に構えるのが一番って事だな」
「………そう、ですね」
儚げに微笑うセイドリックに、ウィルナードも笑顔で応える。
ヴェルヌは一度盛大なため息をついてから、それでも、直ぐに苦笑いを浮かべる。
平和、だったのだ。
その日の、その時までは。
いつものような一日を過ごし、兄弟揃って『夢』の話をしたその日。
やがて降りた夜の帳に、名残惜しい気持ちを残しつつ、互いの私室へと別れてベッドへもぐりこんだその日。
――――――『異変』は、夜半に起こった。
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
